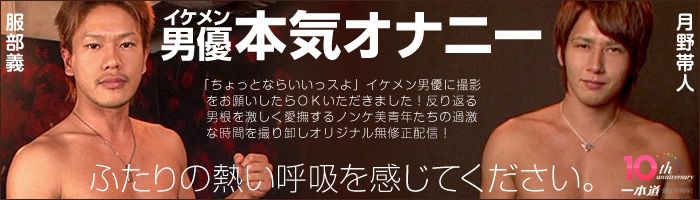�u���{�v�Ƃ̕��������邱�Ƃ��Љ��_���������Ŕ��\���ꂽ�B�掏�͂U�V�W�N��
��ƍl������Ƃ��Ă���B���{�Ɩ����悤�ɂȂ����̂͂�����Ȃ̂��͌Ñ�j��
�傫�ȂȂ��B��߁i�V�O�P�N�j����Ƃ̌������L�͂��������A�掏���{���Ȃ�
����ɂ����̂ڂ邱�ƂɂȂ�B
�@�����̕掏���������閾����̋C���ۋK�����i�����j�j�ɂ��ƁA�_����
�g�ё�ÐЌ������̉��A�������w�p�G���u�Љ�Ȋw����v�V�����ɔ��\�����B
�I�R�i�ł�����j�Ƃ����S�ρi������j�l�̌R�l�̕掏�łP�ӂT�X�Z���`�̐����`�B
�W�W�S��������A�U�V�W�N�Q���Ɏ��S���A���N�P�O���ɑ���ꂽ�ƋL����Ă���B
�@�S�ς��~�����߂ɓ��{�͒��N�����ɏo���������A�U�U�R�N�ɔ����]�i�͂������j��
�킢�œ��E�V���i���炬�j�A���R�ɔs���B���̌�̏�掏�́u���{�P���i����
���ւ�ɏŁj�@���}�K����n�v�ƋL�q�B�u�����c�������{�́A�}�K�i���{�̕ʏ́j��
��������A����Ă���v�Ƃ����Ӗ��ŁA����������ŊJ���邽�ߕS�ς�
���R�������I�R�����{�ɔh�����ꂽ�ƋL���Ă���ƋC����͐�������B
http://www.asahi.com/culture/update/1022/TKY201110220586.html
��̕��Ɂu���{�v�̕�����������B�u�ŌÂ̓��{�v�̉\��������
���u�Љ�Ȋw����v�V�����A���A�����̘_���u�S�ϐl�I�R�掏�l�_�v����
http://www.asahi.com/culture/update/1023/images/TKY201110220633.jpg
���얅�q���@�Ɏ����Ă������A�u���o�|�V�q�v�������|�V�q�����]�]�v�̂����鐹�����q�̍�����607�N�ŁA�@����̓���g�萢���Ɏ��������ԏ��u���V�c�h�����c��v������2�N�ゾ���B
��=���̖{�Ȃ�āA�Ñ�l�ɂ����Ă͕��ʂ̔��z�ł��������B
������̋L�^�Ƃ��ďo�Ă������ƂɈӖ�������킯�B
���u���o�|�V�q�v�������|�V�q�����]�]�v
����̂ǂ��Ɂu���{�v�Ə����Ă���̂��ˁB
����=���̖{�Ȃ�āA�Ñ�l�ɂ����Ă͕��ʂ̔��z�ł��������B
�`�l�����{�ƌ����o�����̂�7�`8���I�̂͂��ł��邪�A
�N�́A�`�̐l�X�͌Ñォ�玩�������̍��̂��Ƃ���{�ƌĂ�ł����Ƃ����̂��ˁB
http://www.baidu.com/s?wd=%C8%D5%B1%BE+678%A1%A1%C4%B9%D5I&rsv_bp=0&rsv_spt=3&n=2&inputT=687
�����]�̔s��̃V���b�N�ł킸��15�N�̊Ԃɑ�}���ʼn��������낤�ȁB
�u���{�P���i���� �ւ�ɏŁj�@���}�K����n�v�̓��{���āu�����v�Ƃ������
�����Ƃ��������ٖ����̑��̂����肻���ȕ����Ȃ��B
�����]�̐킢�̌�A����Ăč��������ĂāA���̒���ɋ��G�����̐l�Ԃ�
���{�̗���d���ē��{�̐V�������䒚�J�ɂ����Ă��ꂻ���ȕ�������Ȃ��B
�Ђ���Ƃ���Ɓu���{�v�Ƃ����̂������̘`���ւ̏̂̕Ƃ܂ł͂����Ȃ��Ă�
���̂������\��������̂ł́H
�ŁA�`�����{�͑嗤�┼���ł́u���{�v�Ƃ��u�`�v�̑��̂����炩�̌���̉���
���������Ƃ��Ă��܂����̂ł́H
���̕��̑S���A�܂��͑S�ʎʐ^�ĂȂ����ˁH
�ȑ̎��ł��������ǁB
�u���{�v�Ƃ����͈̂ӊO�������ȁB
��̎傪�S�ς̐l�Ԃ����炱������Ɠ��{�ɋ`�����Ă����\���������͂Ȃ��B
�掏�͖��߂Ă��܂������l�̖ڂɐG���댯���������낤�B
���{���P噍�A�}�K�ɋ����A�Ȃ����n��療��B
���{�͐����c��A�}�K(��C�̒�)�ɋ����A�Ȃ����n���B
����10���������œǂ߂A����ȂƂ��납�ȁB
�����B���S�ς̐l�ԂƂ��āA�S�ς��������Ă��ꂽ�`���C�̌������Łu���{�v�Ƃ�������Č��݂Ȃ̂���S���ł���A
�Ăȕ����Ȃ̂��Ȃ��B
�ǂ݂̂������̋L���������ች���킩��Ȃ���B
�V�����{�̈˗����āA�u���x"���{"�Ƃ����V�����ɂ��܂����B���̐V�������O�œ��Ƃ̊O���W�����P�ł��Ȃ���
�����݂��Ă���܂��H�v�Ƃ����������Ă����̂����B
������B���������̐��E���Ȃ�(���B
�u���{���̎c�]���́A�����̓����ɓ��S�����v�Ƃ����Ӗ��B
�}�K�i�ӂ����j�Ƃ͓��{�̓���i���m�ɂ͊֓����ʁj�̂��ƁB
���������B�m�����ӂ�́A���������������E�f�����B
���}�K(�����ƒ��ׂĂ݂���)
���`�́A���C�̓��̏o��Ƃ���ɂ���Ƃ�������Ȑ_�B
�]���āA�����C��ɂ��铇���B�}�K�E�}�K���́A���{�ُ̈̂Ƃ��Ȃ����B
���ׂ��牽�ł�������Ǝv�����Ⴂ���B
�}�K�Ƃ����̂́A��`���܂��s����Ȍ��t������ȁB
���{�l�������}�K����Ȃ����B
���{���������d�l���߂ł͂Ȃ��A
�u7���I�̒����l�v���}�K�Ƃ������牽�̈Ӗ������邩�̖�肾�B
���̕��͂ł́A�u��C�̒��̓��v�Ƃ����Ӗ��Ŏg���Ă���͖̂������B
��邠����������ȁB
����ɂ��Ă��ǂ������Ă������Ƃ��Ȋw��������ȁB
�ȁ[�ɂ��A�u���{���P噍�A�}�K�ɋ���A�Ȃ���n����v�Ɠǂނ��B
���̖|��̂ق�������ۂǕ�����₷�����낪�B����炭����
噍�́u���ށv�Ƃ����Ӗ��̂₤�ł����B
�����Ƃ������͕̂����̈Ӗ������B
���ӁE��������A�ǂ̈Ӗ����̗p���邩����ǂƂ������̂��B
�����̂��ʂ̈Ӗ����������ƁA���ꂪ�ǂ������B
�����܂ł��Ȃ�A
���݂������Ӗ��ʼn�ǂ������͂���Ă݁B
�c�_�̃C���n���狳���Ȃ�����Ȃ��̂���?
>�����Ƃ������͕̂����̈Ӗ������B
噍�ɔs�c���ɗނ���Ӗ�������Ƃ̃\�[�X��������肪�����B
�u���̕��͂��������Ӗ����낤����A
���̊����ɂ͂��������Ӗ�������͂����v�Ȃ�Ďv�����݂̓i�V�ŁB
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history/1313686331/
�V�c���̕�����ɐ������Ă���ł��傤�B
�ߍ��͂܂��A���������Ă���̂ł́H
���ǁA�̂��猾���Ă���Ƃ��肾�����̂ł��傤�B
����͖����ɗR������ƍl�����Ă���B
>噍�ɔs�c���ɗނ���Ӗ�������Ƃ̃\�[�X������c�c�c
�u�s�c���v�ȂǂƂ����Ӗ�������Ƃ͏����Ă��Ȃ��B�u�����c�����v���B
�u�]噍�v���ǂ����߂��邩�B
�ق��ɉ��߂̎d�������������o���̂��ӌ������A���_�Ƃ������̂��B
���̖{�̍������{����
���܂�����u���ފ݁v���炢�͒m���Ă邾�낤���A����́u�ނ����݁v�Ƃ����Ӗ���
�܂�u�Ѓm���ƃm���Ɂv�Ƃ͔����`�l���炷��ƁA���{�C�����Ȃ���u�ނ������̖{���v���w�Ђ̖{�̍��x���Ƃ�������
�a��̉��ɓ��Ă銿����`���a�Ɖ��߂��悤�ɁA�u�q�ɓ������Ă��v���Ă킯����
�������v���������ǁA��u�ł��i�b�g�N�������ɂȂ������͋�����肢�܂���
ɼ
���X���l���Ȃ���ǂ�ő�����w
����Ȃɉ����������̂��ˁB
���������ɂ͘`���ł�
������
���������Ɂu�`�v�������̂𒆍������Ɂu���{�v�ɕύX�������Ă��ƁB
�����ł̓��}�g�̂܂܂ł����Ȃ��B
�}�K�́u�}�v�̕����͌����Ă�݂������Ȃ��B
�}�K�Ƃ͓ǂ߂B
�������@������
�Ȃ�œ��{���Ȃ�����
���ƂɂȂ��
���{���I�ɂ�������o�Ă���B
�H�R��672�N�܂ŐV���ɂ����B
���́u�`���v�͋��`�́u�`���v���ޗnj��łȂ��A���炩�ɑΔn���܂ލL�`�́u�`���v���u��`���v�ł���̂�
���̎��͂܂��u���{���v�łȂ��u�`���v���������A
���̎������_�@�Ɂu�`���v�́u���{���v�ɕς�����̂ł͂Ȃ����B
�����͎O�B
�@�V���V�c�S�i�U�V�T�j�N�P���ɓޗnj����u�`�v�łȂ��u��`�v�ƋL�����L���������B
���`�́u�`���v���ޗnj����u��`�v�ƋL������͐鉻�V�c�ȑO�ɐ��Ⴕ���Ȃ��B
����͍L�`�́u�`���v�̍����ύX���Î����Ă���B
�A�V���V�c�R�N�́A�O��̔N�ɔ�ׂċɒ[�ɋL�������Ȃ��B
�u���{�v��_��ɑk�点�邽�߁A�����ύX�̋L�����ȗ��������B
�B�V���V�c�S�N�͏j�ꃀ�[�h�����܂�A�V���̉��q������^���i�ϏB���j�̉��Ɣ@�����{�ɗ��Ă���B
�����ŗ����ɍ����ύX��`�����̂��낤�B
�Ɩ������i�������j
����Ɠޗǁi�Ȃ�j
���J�Ɣ����i�͂��j
�݂����Ȃ���ŁA��{�I�ɂ͐V�����\�L�@���������Ƃ������ƁB
�܂��m���ɓޗǎ���ȍ~�A�ΊO�I�ɂ����{�S���Ƃ��Ă̍������u���{�v�Ƃ��Ă���߂͂��邯�ǁA
����ŏ̓��V�c�̏ق▜�t�W�ȂǁA�ޗnj��̂�܂Ƃ̂��Ƃ��u���{�v�ƕ\�L���Ă���������B
�r�₦�Ă��������������āu���v�Ɖ����B
���̌㌳���͓r�₦�邱�ƂȂ��u�����v�Ɏ���B
�U�V�S�N�̋���A�S�Ă̐_�X�ɕ����S�Ă̊����ɔz��Ƃ����呛���Ȃ̂�
�����L���������B
�����ύX�����Ȃ�A�����̃W�p���O���W���p�����W�b�|�������{�̏o���_���B
�u�S�ρv�ˁu������v
�u�C�߁v�ˁu�݂܂ȁv
�u�����]�̐킢�v�ˁu�͂������̂��̂��������v
�ł����̒��w���⍂�Z���̋��ȏ��ɂ�
�u�V���v�ˁu�����v
�u�S�ρv�ˁu�ЂႭ�����v
�u�C�߁v�ˁu���돔��(���₵�傱��)�v
�u�����]�̐킢�v�ˁu�͂������̂��������v
�ɐ����Ă��錏�ɂ��āc�B
��������N�l�ǂ��̉e�����낤���c�H�H
�S�ϊω��Ƃ����ЂႭ��������̂�Ɠǂސl�������Ęb���ʂ��Ȃ��Ƃ��Ȃ肻�����ȁB
�S�ρ��y�N�`�F
����큨�R�O����
�C�߁��C���i
�R���A�ꂾ�Ƃ��������������H
������オ���������̂悤�ɂ݂����������̂ł͂Ȃ�����
�@���瓂�ɕς�����݂�����
���{��͍�����ɋ߂��炵��
�Ȃ��u�����v�́u�R�}�v����Ȃ��āu�R�E�N���v�Ȃ́H
�����A���������{���I�Ƃ��Z���j�Ɂu�����v�͏o�ė��Ȃ���B
�u����v�ƕ\�L���u�R�}�v�ƌP��ł�͂��B
�R���ɂ͋���(����)���Ă����n�悪������ǁA���킩��̓n���l���Z��ł�������u���܁v���ēǂނ�
���Ē��w�ŏK�����B
�C�߂̌��͂Ƃ�����(����͂��Ȃ��)�����]��
�������̑����������Ă���̂Ȃ炻�����ǂ݂���Ǝv���
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1321889143/1-4
�ӊO�ɓ��{�Ɖ����[���B
�u���炬�v�Ƃ��u������v���Ă̂́A�����܂ł�
�`�����ł̓ǂݕ���
�����A�ނ炪���Ƃ����ӂ���
���������̍�����ǂ�ł����̂��A�������̂���B
�����Ƃ����̂́A����ɂ���āA���C���₦���ω����邩��ˁB
���{��͘`�ꂾ��A���ʂɁB
��������Ă̂́A�����̉������}�]����������
�}�]�ꂾ�낤�ˁA�����炭�B
���Ƃ�����A��������Ă̂́A���^��̑c��ɋ߂��Ǝv���B
���c�����C�́A���������낤�H�������B
������A���_�V�c����O�キ�炢�ɁA
���{�Ɉږ����Ă����o��������������B
����{���Ȃ̂��H
�S�ς��A������Ɠǂ܂Ȃ��Ȃ��Ă�킯���B
���t�͍ݓ��؍��n����������
�ނ����͂�������ւ��Ă��̂�
�����B�͖łڂ��������ƋC�Â�����A�Ƃ���ɂ�����������ɂ�����B
����Y�B
�\�[�X���ڂ�
�u�V�����v�u�y�N�`���v���������B���ꂪ��ԋ߂��B
������č����݂̊؍���ǂ݂���B
���{�����������āu������v�u���炬�v�Ƃ���
������U���Ă��������悭������B
���ǂ݂Ƃ��؍���ǂ݂Ƃ��Ⴄ��ˁB
�v�z�Ǝv�l��������̐l���ĈӖ�����H
�u���{�v�́u�C���{���v�����j�I�ɂ͐������B
�������Ɏא��B���ꂾ�Ƃ��炬�������̐���������B
>>64
�S�όꂩ���H
�Ƃɂ����؍��̐l�������ǂ݂͂�߂悤�B
������
�����j���̋L�q�ɂ��A�}�]�E�������E���C�E�S�ρi�x�z�w�j�̊e����Ƃ͓��n�Ƃ���A
�������k�����璩�N�����k���ɂ����ĕv�]�n����Ƃ������ׂ�����O���[�v���`�����Ă����炵���B
���̌���O���[�v�͉��C�B�̃��E�K�Ƃ́A�u�e�e�͎��Ă��邪����͈قȂ�v�Ɓw�㊿���x��w�O���u�x�ɋL����Ă���B
�܂��A���N�����암�ɍL�����Ă����،n����i�n�E�يE�C��ÎO�̌���B
��̕S�ς̔�x�z�w�̌����A���N��̒��n�̑c��ɂ�����V��������̃O���[�v�ɑ�����j
�Ƃ�����I�Ȉٓ��������������悤�ł���B
�č\���ꂽ�������b�Ǝ��ӌ���Ƃ̔�r�̌��ʁA������͒������N����������{��Ƃ̕����A
�ގ��ꂪ���o����銄�����傫���Ƃ�������������B
�܂����{��́A������Ŕ������Ă��鐔��4���ׂĂɂ����ē��{��Ƃ̊Ԃň��̉��C�I���ʐ����F�߂���Ƃ��āA
���{��̋N���Ƃ��čl���錤���҂����݂���B
�S�ό�́u�N���i���v���痈�Ă�ƌ����Ă�B�l�[�f�������h���I�����_�ɂȂ����̂Ɏ��Ă���B
�S�ς͌��n�ł́u�y�N�`���v�ɋ߂������������͂����B
����ł��؍���ɂ͂������Ȃ��B
�u������v�͐V���A�����A�����Ƃ��Ɠ�������Łu�����v���������낤�ȁB
�u�S�ρv�́A�i�������͕ς����j�S�ς̎��ď̂���B
�؍���Łu�N���i���v���u�傫�����v�̈Ӗ��ŁA�S�ϐl�������̍��������Ă�ł����̂��A�����Ɗ��Ⴂ�������{�l��
�u������v��S�ς̓ǂ݂Ƃ����B�Ƃ����������猻�n�ł́u�S�ρv�̔����Ƃ͊W�Ȃ��B
�I�����_���{���̓l�[�f�������h�Ȃ̂ɓ��{�l�̊��Ⴂ�ŃI�����_�ɂȂ����B
�w��̍��ŃN�_��������H
�Ă̍��́A�R���������璩�N�����A���C�B������{�̓��{�C���ɂ����āA�S���܂�̏������������A
���Ղ�ʂ��ɂ₩�ȓ����W���ێ����Ȃ��甼�_�����Ő��v�𗧂ĂĂ����̂��낤�B
���̑��̂��S�ςƌĂ�A���̓s�A�S�Ă̓ޗǁA�u�ЂႭ�Ȃ�v�A�u���Ȃ�v�A�u������v�ƂȂ����Ǝv���܂��B
��B�̔ֈ���S�ρA�C�m�����ł���āi���킢�j�̈ꍑ�ł���A�V���̐Đl�ƌ����A�E�����͂ƑΗ��������߁A
�і쎁�ɂ���ē����ꂽ�̂��낤�B���ꂪ�ֈ�̗��ƌĂ�Ă��܂��B
http://homepage3.nifty.com/kiya/sehachi/kiya32_c.htm
�u�O���j�L�`�V���{�I�v������10(670)�N�A�`���A���炽�߂ē��{�ƍ�����B���猾���B���o�鏈�ɋ߂��A�ȂĖ��Ƃ���B
�Ȍ�(����V����)�A�`���u���{�v�ƕ\�L�����B
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history/1292521488/
>220 �F���{�������j����F2010/12/19(��) 23:03:51
> >>214
>
> ���̌����Ă܂��`�A�ɎQ���̈⑭�ɉ]��
>
> �W�̎��A����킷�łɗɓ��𗪗L���A�S�ς܂��ɐ��ɋ��L���A�W��S�炷�B
> ������E�k���̊ԂȂ�B
> �W���Ȍ�A������ە����A�n�̌̒n�����L���B
> ���̍������Ɏl�S���A��k�ɋ�S���A���V���Ɛڂ��A�k�������Ɛ�]���������B
> �W���݂��A����S�όS��u���B
> �S�ρA�����㊿���̕}�]���сA�w��̌�A���鰂̎��A�S�ω��A��\���ĉ]�킭
> �u�b�A����ƕ}�]��悸�o�ÁB���߂ĕS�ƊC���ς��A���݂ĕS�ςƍ����B�v
>
>
> ���̌���͏��āA�܂��`��ɂ�������Ă����◬���̌����Ă������̂ł���B
>
> �W�̂Ƃ��ɍ����͗ɓ���̗L���A�S�ς͗ɐ���̗L���Ă������A�W�͂��̓�S�炰���B
> ������E�k���̊Ԃ̗̈�ł���B
> �W����A�S�ς́A�����ۂ��A�n�̌̒n��̗L�����B
> ���̍��́A������400���A��k��900���ɋy�сA���V���Ɛڂ��A�k�͍����Ƃ��悻1000���̊Ԋu���������B
>
> �W����O����̗L������̂Ƃ����ʂ����A�݂�����S�όS�𖼂̂����B
> �S�ς́A�㊿���̕}�]���сA�w��̖���ŁA鰂̂Ƃ��A�S�ω��͏�\���Ă��̂悤�Ɍ������B
> �u�������́A�����ƂƂ��ɕ}�]����o�āA���߂Ă�������̕����̂��̂ƊC���킽�����B
> ������A���t���ĕS�ςƍ����Ă���v
>
> �ނ����E�E
http://www.interq.or.jp/www-user/fuushi/5-anc/kodaisi/ka-c8-fujiwara.htm
�������͒��b�������������Ă���̈ꑰ�Ɖ]���܂��B
���オ���������ł��B
�Ƃ��낪�A���b���͂��̌���ʌn�ő������Ă���̂ł��B
�v���ɁA���b���Ɠ������͕ʌn�ł͂Ȃ����ƍl�����܂��B
�����́A���b���Ɉ�U���薹���A���̌�A�������ĕ��h�����ƁB
�Ɖ]���̂��A���b���́A�����j�M�Ƃ��č��J���i��ꑰ�ł����A
�������ɂ͂��̗l�ȗႪ�����܂���B
�ؔ����암�̓`���ŁA�������́A�S�ϖp���̏o���ł���Ɖ]�����̂�����܂��B
�����炭���ꂪ�A�������̏o���𐳂����`���Ă���ƍl�����܂��B
�S�ϖŖS�O��ɓn�������ꑰ���Ǝv���܂��B
�����ɂ��ẮA��ʂɁA���I�����ւ̏����ɂ͗p���܂����A�ʏ̂ł͗p���Ȃ����Ƃ������̂ł��B
������̓������͒��b�������p���Ă��Ȃ����Ƃ��A��L���@�̗��t���ɂ��Ȃ�܂��B
���_�A�S�ς͓��ɔ��R���A�ł�ł��܂�����A�p����p����͂�������܂���B
�����炭�A�S�ω����ɋ߂��ꑰ�ł��������߁A���̌���{�ɂ����Ă������ɋ߂��ʒu��
��߂Ă���̂��ƁA�l�����܂��B
洎�V����O�\���@�q龍�N�h�сi�T�S�P�N�j�O����.�L���H.�������뚠���N��㑷�w�Չ��V
�~���c����.
�ʌȉK�N�i�T�T�X�N�j�u�֖[,�~�y�w�Ւ���,�O�S�O�\�ڔV��,���_禮��,�i�����.���T�w�Վ��ʋ���.
�V���{�I���
�Q�O�X�N �Y�㔪����������N���A�������q�̋~���v���ʼn��R�𑗂�B
�w�Ւ����k�T�S�P�N�l�łR�R�O�N�ł��邩��A���댚���͂Q�P�O�N���ł���B
�V���{�I�ł͂��̎��i�Q�O�X�N�j�����ɉ��R�𑗂�B
鰎u�`�l�`�Q�R�X�N�ɂ́A��؍��i�J���J���R�N�A��������A�C�߁j�͑��݂���B
�הn�䍑�Ɗy�Q�S
http://homepage2.nifty.com/mononoke-kofun-room/HP/shiten3yamatai.htm
�Q�P�O�N�@���_��
�C�߂�蒩�v�@�R���I�O���̑�^����
���m�ɂ��c���Ԏ�h��
�z�P�m�R�Õ��@�i�Q�Q�T�`�Q�T�O�N�j�y�Q���A�S��͔C�߈Ȍ�
��������i�����R���j�͏����̏��ց����m���B
�i�Q�Q�T�`�Q�T�O�N�j�ɐ��m�Ɠc���Ԏ��T���A�s�s����(��������j���^�W�}���� ���c���Ԏ�
�Ɏx�n���C�N�������m
���m�����Q�R�X�N�Ƃ���ƁA㕌��͂Q���I���ɐ��_����͂��܂�B
���x�����R�U�X�N���琒�_=�ږ�āi�Q�S�O�N�j�͊���o���ꂽ�B��P�R�O�N��
�V�ҔN
���_���Q���I�������P�R�O�N�オ���x�����R�Q�U�N�ł���B
���a�I���@�ޖܑ吹�_��I(�l�����f�\���O�V���[�M) 1�N, 11��, AD377�N. (ver.1)�@�B
�R�P�V�N�@���N ���N �\�ꌎ ����N�獎�� ���d�� �Ȑ鎸�ב��@ ������^�`����
�s������V�� �����Ș`������ ���s���鎸�V�� ���g�ӔV
�R�P�V�N����Ƙ`�͒ʂ��Ă���A����ɏ]��Ȃ��A����͉��낪�`�������ȂƂ������߂ł���B
�R�P�U�N�@���W�ŖS�B�m���S�N�ۖ��̒�~�B
��F���F 383�N�� �l.�@Name�Fradio2010/06/04(��) 17:38
�ޖܑ吹�_��I(�l�����f�\���O�V���[�M) 7�N, �@ �F�F����F���F
�R�Q�R�N�@���N ���� �s���r�� ���b�ɔ��� �����g�� 7�N1��, ���r(ᡖ��N)�Ղ��s�����B
�O�� �v�]�����O�\�˖����~ �v�]�^�`���� �N�N�� �U�u�s� �`�b�F�F�����P�� �^�������� �������� �̍��l�ٔ� ���A���� ���A���� �x�瑾�@����?�q��? �n���ˌ��T �֖��q�ꑊ��
3���@�}�]�̗������܂��R�O�˗��~���Ă����B�}�]�Ƙ`�͒ʂ��Ă���A�N�X���̖�������
�s�⑺�ɎU�u���Ă����B�`�b��F���F�͗ǂ��ِオ�����A�Z���ƒ����悢�B
�Z���͂��̌��̑���������A�̂ɍ��ɔw���A��F���F�ɏ]���B�i��ʓn���j
�����͉�i�S�ρH�j�ɋA���A�܂������ɋA������B
�R�Q�R�N�@�_���S�X�N�@�����苒�Ɨ̓y���^�B
�����V�c�Z�N�i�����l�Z�܁j�@�ߍƁB��Z�����|����B
���́g�Z���h�Ƃ́A������������Ȃ��B
�S�O�V�N�@�\���N�����͌����R���݁D�D�D����a�E��ᶏ��t�Z�����P�́D�D�D
����̓������������B
�S�P�R�i�`꤂X�`���]�A�g���𗧂Ăē��W���v�i�w�W���x�w�����䗗�x�j
�i�w�W���x��I��\�@����j���`ꤋ�N�k�S�P�R�l�����@�`���y����Γ�����t���ٕ���
�v���ɋ�\���^��B��\��
������鋚��A�������V�ɓ��S�B����鋉����l�A�����`ꤋ�N�A�����j�����A��\���ޔ��n�B���l�Ag���߁A
�s�z�B���R���A�������R�A����鋉��A�٘Q���B���c��阼�A�ٞH�u�g���ߓs�z�B���R���������R����鋉��٘Q
���l�A�g���ߓS�Z���R���������R�S�Z���f�C�����`�C�O�C���C�v�E�B�ҐV���n�A�X�ך��x�A�l�����囒�R�A
�f�����囒�R�B���ߓs�����A�@�́B�v
�S�ς͍����Ɋ܂܂��B�i�S�ρE�V���͍����̑����j
�V�c�O�N�i�b�Ўl��l�j�����@��g�����Ή��V���B�V���͍����̑����ł���i�m���܂ł̈����ł͂Ȃ��j
�V�c��l�N�i����l�O�܁j�Z���@�L�����B
����Ȃ璆���j���n�ؓ`�ɂ�����ɋ߂�����������ׂ�����Ȃ��H
�V�����z�������Ȃ������킯����
���{�����ł͐V���l�̖��O�͓��{�l��S�ϐl�Ɠ������������炵�����O���������j���ł͂قڐ��Ă���
���V�c�������ꎚ�Ă���݂̂������肷��
�ږ�Ăɂ��Ă����{��ɗނ���̂́u�Ђ߂݂̂��Ɓv����
�����j���𖼏̂Ȃǂł��Ăɂ��Ă͂Ȃ�Ȃ�
�����̓��{�l�����퐶���ł��̖��O���g���ĂȂ��������낤�B
���Ƃ����@���ł͓V�c�̖����u���̓A���A���̓^���V�q�R�v
���Ȃ킿�u�A���^���V�q�R�v�Ƃ����������炵�����������ڂ������ŁA
�u���̓I�z�L�~�v�ƕ��i�́u�剤�i�������݁j�v�ƌĂ�Ă������Ƃ��ڂ���B
���Ƃ���t���̐������̂����������Ƃ��Ă��A����ǂ݂��u�Ђ݂��v�������\���͏\���ɂ���B
���Ȃ݂ɓ��{�̍c�������̔��㍠�̌Ăі��͈ꎚ�Ⴂ�́u�Ђ߂݂��v�������B
鰁E�W����V���͒C�ɑ����B
323�N�@�_��49�N�@�V���͘`�ɑ����B
���̎��S�όR�͑��݂���B�S�ς͐V���ƑΛ����Ă����L�^�����邩�狫��ڂ��Ă���
�S�όR�Ƃ͒C�̌R�Ƃ��ċ@�\���Ă����Ǝv���邪�A323�N���_�Ř`�̗v���������
�����猩��Α債�����͂ł͂Ȃ��B
���{���L�́u�������N�i687�N�j3��15���u�����̐V���l14�����Ȃ��āA���і썑�ɋ��炵�߁A�c�������A�g���A���ƂɈ������ށB�v
�Ƃ����L�q�Ɠߐ{������̋L�q�͕������A�����̐V���l���ߗ��Ƃ��ĉ��썑�Ɉ��u���ꂽ���Ƃ͊ԈႢ����܂���B
�́C�V�i�l�͓��{�̐l�Ԃ����W���C���R�N�Ƃ����C�`�l�C�`���ƕ\�L�����B
���{���͎�������}�g�Ə̂��C�V�i�l���\�L�����u�`�v�Ɂu���}�g�v�ƌP�݂������B
���̂����āu��`(�I�z���}�g)�v�Ƃ������C���̊Ԃɂ��u��a�i���}�g�j�v�ƂȂ����B
���l�Ȏ�������ɂ��������̂��낤�B����Ȃ̂ɐV�����V���M����V�����֓ǂݑւ���
�Ȃ�āC��a���i���}�g�^�}�V�C�j���_�C���R���Ɠǂ݂Ȃ����悤�ȋ��ł��낤�B
�n���������ɂȂ�̂͌��\��K�͂ȌR�����ꂪ�K�v�Ȃ�Ȃ����낤��
�u���}�g�v�������ɂȂ������Ƃ͂Ȃ���Ȃ����B
6���I�ȑO�ɂ͒�������u�`���v�ƈ���I�ɌĂ�Ă������̂�
6���I�O��ɓ��{������u���{�v�Ƃ��������𒆍��ɓ`���Ă���B
���{�ŏ��߂Ăł������������{�B
����ȑO�ɂ͂܂��E���𒆐S�Ƃ��鏬���A���ł�����
��̍��Ƃ����T�O�������ɂ��������ǂ����͕�����Ȃ��B
�����ł̐V�����\�L�@���������ɂ����Ȃ��B
���������E������
�Ȃ灨�ߗ��E����
�͂��������E���J
�������u�M�E���
�������F���E�p��
�Ȃɂ큨��g�E�Q��
��܂Ɓ��`�E���{
�S���Ⴄ�A�{���́B
�u�����W�����Ƃ��m�����A�`��������{���ɍ��������߂��]�X�v
�č��荞�܂����߂����Ǝv���ˁB
���ۂ͂ق�Ɗ����ł̏������������������̘b�ŁA
�`���E���{���ǂ����Ƃ������I�ɂ́u��܂Ƃ̂��Ɂv�������Ǝv����ˁB
�ޗǎ���ȍ~�u��܂Ƃ˂��v�\�L�ɂ͘`���q�����{���q���g���邵�A
���t�W�ł��u���{�v�́u��܂Ɓv�Ɠǂ܂�A����ޗnj��̂��Ƃ��w���킯������A
�u�������w��x����w�ɂق�x�ɉ��߂��v�]�X�Ă̂́A������ƈႤ��Ȃ����Ȃ��Ǝv���B
TOP �J�e�ꗗ �X���ꗗ 2ch�� �폜�˗� ��
�d���ƗH�쁙���ق̓��{�j (105)
���Ð_�����̐z�K���ɂ��Č�� (192)
���{�j��ō��̂������̓V�˂́H2 (170)
�����������q����Ɏ���ړ����Ă���X�����m�\ (139)
�����u���B���ᒷ�B�̎d�Ƃ���`�I�v (162)
���ȏ��ŗ��j�ɋ����������z����́H (180)
--log9.info------------------
�e�X�g (184)
���� (100)
VIP���炫������ (191)
���̒��q������ (171)
���� (100)
���� (100)
���� (100)
�e�X�g (140)
�e�X�^���b�T�ƌ����ׂ̂��� (122)
�e�X�g (100)
tst (129)
S/mileage (161)
(�L��֥`)��ݼ�� (176)
(�L���ց�`) (118)
�ŋ߃Q�[�����܂�Ȃ��B�B (181)
�̂̂���N�� (114)
--log55.com------------------
�E�}�^���Ƃ͂��Ԃ������p�u���X���S
�j�I�^�̂����ŋ��ɂȂ����L�����E��i��f���o���X��
pixivFANBOX����낤 Part.3
�y�h���}�z���i�}���l���� PART12�y�f��z
�y�J�z�^�������A���`�X��2�yFGO�z
�y�C�y�Ɂz�y��������������17�y�y�������z
�n�����b�`���l��s�X��4
�y�c�Ɂz���Z�n�֘A���݃X���y�s��z